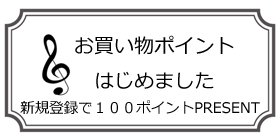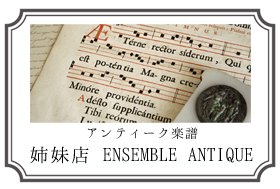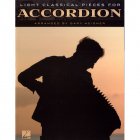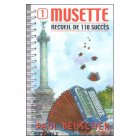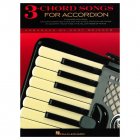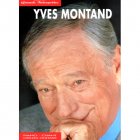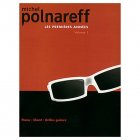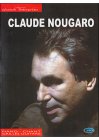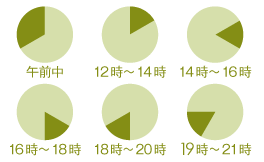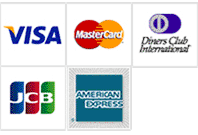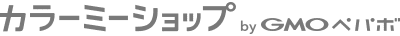1万円以上お買い上げ送料無料♪
日本郵政 クリックポスト
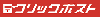
■全国どこでも198円でお届けいたします。
■CDなら3枚程度、A4サイズの楽譜・絵本などがご利用いただけます。
*複数商品のご注文(上記サイズ・重量)に収まりきらない商品に関しては、ゆうパックでのお届けとなります。
- ミュゼット創世記〜初期
大衆音楽として20世紀初頭パリで交流した「ミュゼット」。
現在では,ひらたく言うとアコーディオンを伴った(または伴わない)演奏形態の音楽として知られています。
「ミュゼット」=「パリ・カフェの音楽」は大衆のなかに生まれ,パリっ子の下町の生活から生まれた独得の伝統音楽と言えるでしょう。

1930年頃のバル・ミュゼット *1)
ミュゼットについてお話するのに,この成立に欠かせないが,パリに出稼ぎにやって来た2つの地域の人たち。
それは「イタリア人」と「オーベルニュ人」。
時代は1800年代後半,イタリアの人たちはパリにアコーディオンをもたらしました。
そして同時代,オーベルニュ人たちは,故郷で演奏されているキャブレット(別名ミュゼット)というバグパイプを手に持ち,パリへとやってきます。
パリではそれぞれ同郷のコミュニティのなかで,故郷を偲ばせる音楽にあわせダンスを踊っていました。
オーベルニュ人たちは週末になると,日ごろの気晴らしにとバスティーユ近くのラップ通りなどのカフェやバルに集まり,ミュゼット・バグパイプ,ヴァイオリンヴィエイユ等の演奏に合わせ踊っていました。
このバルでの集まりは「ル・バル・ア・ラ・ミュゼット」(Le bal a la musette)と呼ばれ,それが「ル・バル・ミュゼット」と略されそこで演奏する音楽を「ル・ミュゼット」と呼ぶようになります。
したがって,初めはキャブレットを含むバンドでの音楽が「ミュゼット」とよばれていました。
この20世紀前後にかけて演奏されていたのはオーヴェルニュのブーレやポルカ(La Perigourdine),ワルツなどでした。
一方イタリア人はアコーディオンを演奏し,そのキャブレットのレパートリーや奏法(ピコタージュなど)を取り込んでいきます。

アントナン・ブスカテル(1867-1945) *2)
その中で歴史に名を残すことになるバルとして名前があがるのが,バル「シェ・ブスカル(Chez Bouscatel)」。
キャブレット弾きのブスカテルの娘と,アコーディオン製造者のペギュリ一族のシャルル・ペギュリとの結婚はを象徴的出来事として,以来アコーディオンとミュゼットが繋がり合うこととなります。
1900年前半から30年代にミュゼットの成立に欠かせない代表的なアコーディオニストとしては,
前述したペギュリ兄弟(フェリックス,シャルル,),そしてエミール・ヴァシェ[Emile Vacher]がいます。
今でもアコーディオニストのオールド・レパートリーとして演奏されるのはルイ・ペギュリ《秋風:Ven d'automne》,ミシェル・ペギュリ《ミュゼットの女王:Reine de Musette》,そしてエミールヴァシェ《3連符:Les Triolets》,《真実のミュゼット:La Vrai Valse musette》など。

エミール・ヴァシェ((1883-1969)《Les Triolets》
ミュゼットを調べ始めて有り難いと思うことは,当時の楽譜が現存していて,さらに演奏録音が現在でもCDで復刻していて聞くことができる所にあります。
ワルツ・ミュゼトの基本的な形式としては,第1モチーフ,そして変奏が続き,3番目にトリオという構成が挙げられます。
初期のミュゼットのメロディを彩る装飾音は,《3連符》を聞いても分かる通り文字通り3連符,モルデントなど同音・近接音による装飾,アルペジォやスケールといった比較的素朴な響きによるものです。

当時はエミール・ヴァシェのように,まだダイアトニック式(押し引きで異なる音階が出る)のアコーディオン奏者が多かったため,その楽器の特性からくるものであると思われます。
ミュゼット初期にもう一つ欠かせない形式に「ジャヴァ(Java)」があります。
シャンソンでは《青色のジャヴァ》にはじまり,ピアフ《アコーディオン弾き》に歌われ,ボリス・ヴィアン《原子爆弾のジャヴァ》,クロード・ヌガロ《ジャズとジャヴァ》,そしてゲンズブールの《ジャヴァネーズ》等々,ミュゼットの代名詞的扱いを受けている形式です。
《青色のジャヴァ:Java Bleue》『フランスシャンソンの1世紀 1929 - 1939』

名前の由来ははっきり分かっていません。
諸説によるとエミール・ヴァシェが弾いていた“バル・ドゥ・ラ・モンターニュ”の店の主が,客席を回る時にかけた言葉「サヴァ?サヴァ?」がなまっていて「シャヴァ?」→「ジャヴァ」になったとか。
その時に演奏されていた曲《ロジーナ》[Rosina]がジャヴァの原型のマズルカでした。
リズムとしてはどちらも3拍子で強拍が1拍目にあります。マズルカの場合,曲頭から3連符や16分音符など細かい音の器楽的旋律で始まるのに対し,ジャヴァでは歌謡的メロディのものが多く,それがヴァリエーションで装飾されます。
聴いている印象だとマズルカの方が古典的で,クラシックのように楽譜に書かれている音を演奏し技巧的なのに対し,ジャヴァはリズムをより重視しているように感じられます。
マズルカ:《Coup de Tete》『ミュゼット:110曲 Vol.2』

ジャヴァ:《Chaloupee》『ミュゼット・ヒット曲集 Vol.1』

- 中期
以上、初期のミュゼットの次に来る新しい響きが「ジャズ」の影響です。
ミュゼットへのジャズの影響は1930年代から顕著に見られるようになります。
それまでにもタンゴやスペインのパソ・ドブレなどパリの都市大衆音楽らしく多様な要素を取り込んできたミュゼットですが、響きの面で言うとやはりジャズの影響は革新的なものでした。
もとよりミュゼットには3連符が頻出し,スウィングのリズムに適応しやすい基盤があったとも考えられます。
1930年-50年代には,インプロヴィゼーションの鋭い感覚と並はずれたテクニックを持つアコーディオン奏者が次々と活躍していきます。
その先駆者としてのギュス(グス)・ヴィズゥール、、ジョゼフ・コロンボ,節度あるエレガントなスタイルのトニー・ミュレナなど。
彼らはバルでアメリカのスタンダード・ジャズを演奏しながら,ミュゼットにジャズ特有のシンコペーション,モダンコードをを取り入れていきます。
そしてこの頃もうひとつ,ミュゼットに影響を与えた人物がギターリストのジャンゴ・ラインハルト(Django Reinhardt:1910-1953)です。
マヌーシュの影響も受け《モントーバンの火》,《アンディフェランス》,《パッション》,《スウィング・ワルツ》といったマイナー・スウィングが作曲されます。
《Je t'aime… (SWING 39)》:ジャンゴ・ラインハルト

ここで面白いのはジャズ・ナンバーには2拍子系が多いのにミュゼットはダンス曲として3拍子系が多く,ミュゼットの中へジャズが取り込まれることによって,いわゆるスウィング・ワルツやマヌーシュ・スウィングといった独特の曲想が発展していきます。
そしてこの頃若手として,またマヌーシュ・スウィング奏者として,素晴らしいメロディを生み出したジョ・プリヴァがいます。彼は1960年のこの時代に『Manouche Parti:マヌーシュ・パーティ』というレコードで,ラインハルトの《ニュアージュ》や《マイナー・スウィング》といった曲とともに詩的でエレガントな録音を残しています。
- 現代まで

バスチーユにあるバル「バラジョー」で演奏するジョ・プリヴァ*1)
彼らはバルから飛び出し,当時普及してきたテレビやラジオ,そしてSP盤に代わるLPレコードといったメディアの発達によって活躍の場を広げてゆきます。
日本人がアコーディオンを聞いて「いかにもおフランス〜!」な音色はほぼこの時代までで確立されます。
しかしながら、1960年代にはフランスにもイギリスからのロックの波,そしてアメリカ文化に押し寄せられ,ミュゼットの興隆に陰りが生じてきます。
ダニエル・コランは「この時代にはアコーディオニストいなくなった。私しか弾いていなかった。」と後年語ります*2)。
もちろんそんな事はないのでしょうが,聴衆の年齢層も徐々に上がっていき,アコーディオンの音を古くさいと思う若い世代のミュゼット離れが起きてきます。
そんななかアコーディオニスト達はロックやジャズなど,次の新しい試みへと模索し始めます。
次にミュゼットが注目を集め始めるには1980年代を待たなければなりません。
世界的にもアコースティック・ギターなど楽器本来のサウンドや,民族音楽などへ関心が向けられるようになる時期でもあります。
当時若手のリシャール・ガリアーノも1970年代はロックの可能性を追及し,電子音での試みを見せていましたが,1983年渡仏していたアルトル・ピアソラに出会い「その音楽に触れたとたん,私は楽器のプラグを抜いた」と語っています*3)。
また,かつて表舞台で活躍していたダニエル・コランやジョエ・ロッシ,ジョ・プリヴァ,マルセル・アゾラ等々が次々とアルバムをリリースしていきます。
21世紀に入ってからは,その賑わいも落ち着きますが,ミュゼットも一ジャンルとして確立し,フランスではガリアーノを筆頭に次の展開を見せています。
ミュゼットやマヌーシュを経てジャズの世界で活躍する,優れたヴィルトゥオーゾのリュドヴィク・ベィエ(Ludvic Beier),フレデリック・デシャンの1番弟子ジェローム・リシャール,ファドやジャズの影響が混じり合いドラマやドキュメンタリー番組、映画の音楽数多く手がけるマルク・ベルトゥミユ(Marc Berthoumieux)など表舞台で活躍しています。
またさらに若い世代でも,日本にも度々来日しているル・バルーシュ・ドゥ・ラ・ソグルニュ(Le Balluche de la SAUGRENUE)はミュゼットを土台にジャズ,レゲエ,ダブなど様々なジャンルの要素を取り込み,アングラな雰囲気を持ちながらも独特のサウンドを聞かせてくれます。
その他,ジョゼフ・コロンボやギュス・ヴィズ−ル,ウィリー・スタケット(Willy Staquet)ら往年のナンバーをさらに洗練させたミュゼットスウィングを聞かせてくれるバンド"Toupie Jazz Musette",ナント出身でフランスやベルギーと各地で演奏するミュゼット・トリオ"Swing of France"など,これからの展開が期待されます。
*1)Krumm,Philippe "L'accordéon - quelle histoire ! "I(ed.Mathilde Kressmann,France,2012) 112p.
*2)ビデオ『パリ・ミュゼット2-新しい息吹-』(GPS GX-8)
*3)Galliano,Richard "Interviews réalisés par Frank Cassenti" dans DVD'Piazzolla forever en Concert' (Sony BMG music entertainment France [distrib.], [DL 2006])
参考文献
・Billard,François Roussin,Didier "Histoire de l'accordéon"(ed.Climats,Framce,1991)
・Faugeras, Laurent "Accordéons : De la Java au Jazz"(ed.Du May,France,2008)
・Krumm,Philippe "L'accordéon - quelle histoire ! "I(ed.Mathilde Kressmann,France,2012)
・渡辺 芳也『パリ・ミュゼット物語』(春秋社,1994)
2015年4月
2024年3月更新